私は現在会社員で給与所得者である。
本業以外に株式取引をやっているのだが、もうかったときは「株式による譲渡所得」が、配当金の支払を受けたときは「配当所得」が生じるけど、いずれも証券会社の特定口座で処理してしまっている。
税理士試験合格者として、あるまじき行為とは思うが、「申告不要」生活を送っている。
あまり自分自身の税金に関心を持たなかったのだ。(あと社会保険も)
前々回で投稿したが、所得税より住民税を多く納付しているのは、実は最近知ったのである。
私が社会人になった頃からそうだったのか、それとも何かのきっかけでそうなったのか、今回はそれを解明してやろうと思う。
| 三位一体の改革

「三位一体(さんみいったい)というと、昭和のスポ魂アニメ「アタック№1」で、寺堂院高校の八木沢三姉妹の必殺技「三位一体の攻撃」を思い出してしまう。
ここでいう三位一体とは、
① 国庫補助金の廃止・縮小
② 所得税から個人住民税への税源移譲
③ 地方交付税の抑制
①~③を一体となって実施して、これまでの国が地方を助けるという構造を、より地方が自立して活動できるカタチに変えていこうとする政策である。
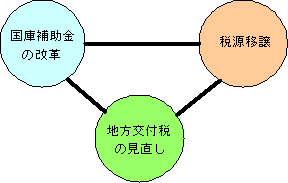
2001年成立の小泉内閣の頃に「小さな政府」を具現化するため、地方にできることは地方に、民間でできることは民間に、をスローガンに推進された。
住民税が多く徴収されるのは、この政策に秘密がありそうだ。
①の国庫補助金とは、特定の施策を奨励するため、または財政支援のため国が地方公共団体に交付するお金である。
国によって使い道が細かく決められており、地方自治体の意思が入り込む余地が少ない。
国庫補助金を減らし、足りない分を国税である所得税から地方税である個人住民税で補填する。これを②の税源移譲という。
この税源移譲は2007年(平成19年)所得税、2007年度分個人住民税より実施された。
このとき個人住民税は一律10%(道府県民税4%市町村民税6%)になったのである。
③の地方交付税とは、国が地方公共団体の財源の偏在を調整すること目的としている。
地域によっては有力な産業が少なかったりしてお金が無いところもある。それを国が助けるのである。こちらも支出を抑制して税源移譲により自立を促している。
地方交付税の原資は、国税でいうと
*所得税の33.1%
*酒税の50%
*法人税の33.1%
*消費税の19.5%
*地方法人税の100%
国税の収入に基づき地方交付税の額は自動的に決まるシステムになっている。
| 税源移譲
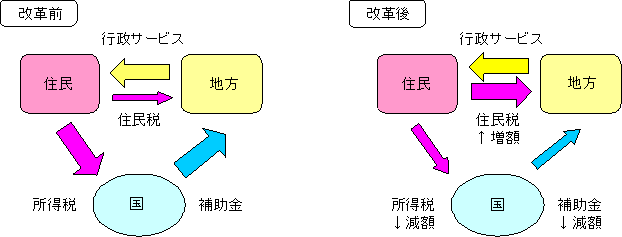
2007年度から個人住民税の税率が変わったということは、同時に所得税の税率も変えられたということである。
国税である所得税の税率を下げ、代わりに地方税である住民税の税率を上げることにより、個々人の税負担を変えないようにしたのだ。
住民税はそれまで3段階(5%、10%、13%)の税率を一律10%(道府県民税4%市町村民税6%)の比例税率になった。
所得の大小に関係なく負担割合は同じになったので、住んでる地域の公共サービスを受ける対価としての性質がより強くなったといえる。
これに対して所得税は、これまでの4段階の超過累進税率から6段階へと変更された。(2020年現在は7段階になっている)
細かい計算は省くが、これによって税負担を変えないようにしたのである。
なお住宅ローン控除で、所得税から控除しきれない分があるときは、住民税からも控除できるようになった。
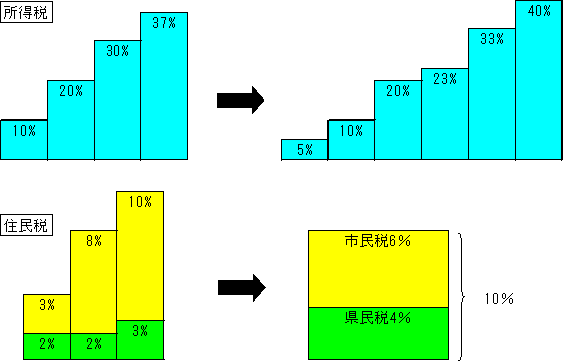
2007年度(平成19年度)は、ちょうど税理士試験の受験を決意した頃である。
このとき既に所得税と住民税の逆転現象は起こっていたのだった。
| 終わりに・・・
私は「所得税法」と「住民税」に科目合格してるが、税源移譲については無知だった。
私が興味があったのは試験勉強であり現実の税金ではなかったというのを思い知ったのである。
ただこのブログを続けていくうちに、ちょっとずつ実際の税金や国家財政の話が好きになってきた自分がいる。
現実の税金は、試験という仮想世界の税金より、もっともっと断然面白い!